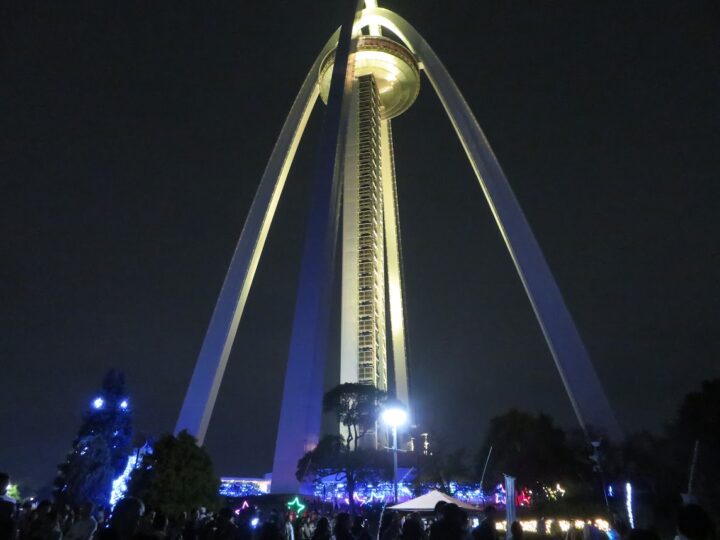1月31日(金)午後2時から一宮市高年福祉課主催の「一宮市高齢者虐待防止講演会」が今年も木曽川文化会館で開催されました。医療関係・介護支援関係従事者・民生児童委員の皆さんなどでホールはほぼ満席状態でした。自主参加研修でしたが、葉栗連区からも10人程の民生児童委員が出席しました。
〇テーマ:『高齢者虐待の防止。早期発見と地域づくり』
〇講 師:日本福祉大学/ 人間環境大学 非常勤講師 ・愛知県社会福祉士会虐待対応委員会委員長
・愛知県認知症施策推進会議委員 塚本鋭裕(社会福祉士・介護福祉士)
テーマが2年続けて高齢者虐待防止研修となった背景の一つとして、高齢者虐待件数の増加にあると推察されます。
厚生労働省の調査結果によると、相談・通報件数が10年前と比較すると令和5年度は40,678件で約1.6倍に増加していました。

高齢者虐待の防止、擁護者に対する支援等に関する法律(通称;高齢者虐待防止法)第1条(目的)の解釈について、
高齢の方が住み慣れた地域の中で、一人の住民として不安なく自分らしく生きがいをもって生活(自己実現)できるよう専門職・関係者として虐待防止法を一つの支援ツール(手段)として結び付けていく。⇒虐待の防止は「地域共生社会」への一歩とも考える
と分かりやすく説明して頂きました。
★虐待と把握する場合の特徴?
①身体の状況 ■不自然な外傷がある、衰弱、混濁、脱水、栄養失調 等
②生活状況 ■おむつが長時間交換されていない、衣服や寝具がひどく汚れている、身体や髪の汚れが常態化している 等
③話の内容 ■恐怖や不安への訴え(怖い、痛い、殴られる)、保護の訴え(家にいたくない、帰りたくない)、自殺念慮(死にたい) 等
④表情態度 ■おびえた態度、怖がる、問いかけに無反応、家族がいる場面で表情が変わる 等
⑤適切な支援 ■家族が受診拒否、介護サービス利用拒否 等
★虐待の疑いについてどのように状況判断するのか?
・高齢者本人が不安、怖いと思っていれば虐待‼ 福祉や介護の専門職として代弁していく力が必要
★虐待の疑いを感じたら?
・高齢者虐待の場合は、市または地域包括支援センターに速やかに通報(一人で抱えず相談)する
・障がい者虐待の場合は、市または障害者虐待防止センターに速やかに通報(一人で抱えず相談)する
最近の虐待事例の傾向として、80歳代の親と40~50歳代の引きこもり、無職の息子や娘が生活している世帯いわゆる『8050』。また、『老々(認認)世帯』配偶者と二人だけの世帯のため、介護への思い込みや対応が一般的な対応から外れてしまう場合。
あるいは、『ダブルケア』親の介護と子の育児等(不登校・障害・疾病等)によりストレスがたまり、子や親にストレスが向いて暴力に繋がってしまうなど課題が複合化していて、高齢者だけの支援だけでは解決は難しい傾向にあるという事でした。
自分たちの地域の問題は、地域全体のこと「我が事」として、公助だけに頼り過ぎず、地域でできることをみんなで少しづつでも取り組むこと「お互い様」が大切な社会となってきています‼
(厚労省:地域包括ケアと地域共生社会)